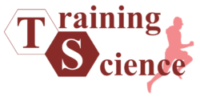【第116回】休み明けは怪我が増える?練習のしなさ過ぎも大きなリスク!
怪我というのは筋力や柔軟性の不足はもちろん、練習のやり過ぎも大きなリスクになりますよね。
一方で、練習のしなさ過ぎというのもリスクになるというのはご存知ですか?
Acute LoadとChronic Load
近年では、GPSや加速度センサーの発達により、球技スポーツの練習や試合の運動量の評価が可能になってきました。
そいうったデータの蓄積から、どういう時に怪我が多くなるかといったことも分かってきました。
ごく端的に言うと、今までかかっていた負荷(Chronic Load)に対して、今(ここ数日or今週)かかっている負荷(Acute Load)が大きくなると怪我をするということが言われています[1]。
研究的にはChronic Loadの何倍のAcute Loadがかかると。。といったことが言われていますが、GPSなどがなければ厳密なコントロールは難しいですよね。
現場での簡便的な活用
Chronic Load(今までにかかっていた負荷)≒負荷への耐性
とも考えられます。
以下のイメージで考えると分かりやすいですよね。

動いていない状態(シーズン初めやテスト休み明けなど)だと、身体の負荷へのキャパシティも減少しています。
負荷へのキャパシティというのは数日で一気に高めることはできないので、急激な練習の負荷の増加は避けましょうということです。
そのため、練習の負荷を構成する要因を把握して、それらの急激な変化を避けることが必要になってきます。
練習の負荷を構成する要因
週あたりの練習頻度
1週間のうち、何日練習するかということです。
週2で練習をしていたのに急に週4で練習をすると、負荷は倍になりますよね。
そういった頻度の急激な増加は避けましょう。
1日あたりの練習時間
1日あたりの練習時間なので、2時間の練習が3時間の練習になれば、負荷は1.5倍ですよね。
意外と見落とされがちなのが、合宿や学校が休みの期間の間の2部練や3部練の場合。
1回あたりの練習時間を7割程度に抑えたとしても、3部練だと1日あたりの練習時間は普段の2倍になってしまいます。
練習の強度
同じ2時間であっても、バスケットボールでのフリースローの練習や、サッカーのパス練習であれば、練習の強度(激しさ)自体は低いでしょうし、ゲーム形式のものであれば強度は高くなるでしょう。
また、同じゲーム形式の練習だとしても、5対5よりも3対3、2対2のほうが1選手あたりの運動量は多くなるので強度は上がると考えられます。
練習の密度(ワーク:レスト比)
同じ練習メニューを同じ時間実施するとしても、特にバスケットボールなどの屋内競技であれば、それを10人で実施するのか、20人で実施するのかで負荷は変わってきますよね。
例えば5対5の練習であれば、10人だと常に休みなしでの実施になり、20人であれば10分動けば10分休みになります。
5対5と3対3だと、実施中の強度は2対2のほうが高くなりますが、練習の密度(ワーク:レスト比)は2対2のほうが高く(=レストが長く)なりますよね。
しかしながら練習で使う場所をオールコートではなくハーフコートにする、1グループが練習している間に他のグループはコートの外で別の練習をするなど工夫をすれば、人数が多くても練習の密度は高められます。
特にサッカーやラグビーなどの屋内競技の選手は練習を実施する箇所の増加は行いやすいですよね。
まとめ
中期・長期の休み明けは怪我が増えます。
これは身体が負荷のキャパシティに適応していないからです。
これを予防するには主な方法は2つあります。
●休み明け前に選手各個人が身体の負荷へのキャパシティを高めてくる
●休み明けの練習量はいきなり高くし過ぎず、徐々に上げていく
どちらかというより、両方を意識して実施することがベストでしょう。
そして練習の負荷をコントロールするには
①週あたりの練習頻度
②1日あたりの練習時間
③練習の強度
④練習の密度(ワーク:レスト比)
をそれぞれ調節する必要があります。
球技スポーツ選手で、ウイルスの影響などで練習場所が確保できないという場合、外を走るのも良い手でしょう。
その場合も、練習の負荷から逆算すると上記の①~④をどのように調節すれば良いかも見えてくると思います。
活動自粛のチームも多いと思いますが、いつ再開しても良いように、各自で準備していきましょう!!
執筆者:佐々部孝紀(ささべこうき)
参考文献
1. Hulin, BT, Gabbett, TJ, Lawson, DW, Caputi, P, and Sampson, J a. The acute:chronic workload ratio predicts injury: high chronic workload may decrease injury risk in elite rugby league players. Br J Sports Med 50: 231–236, 2016.